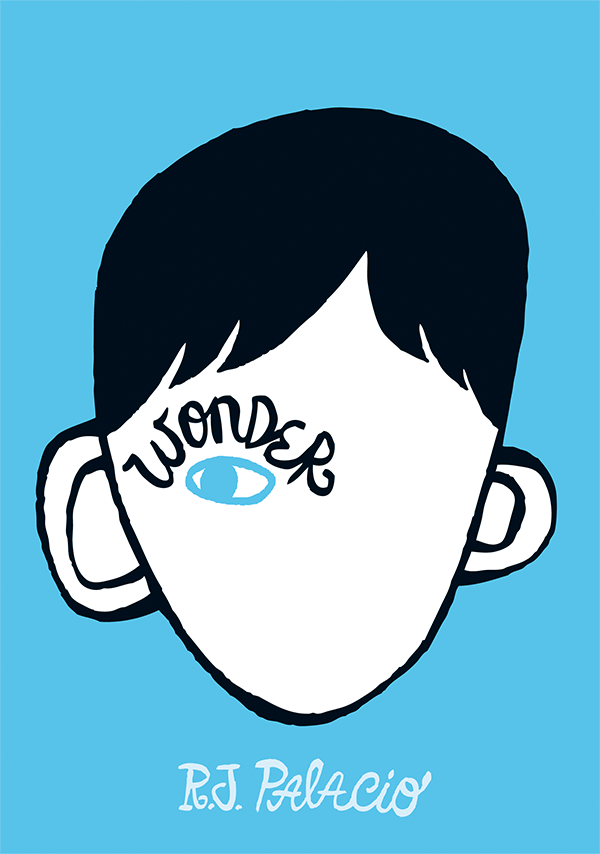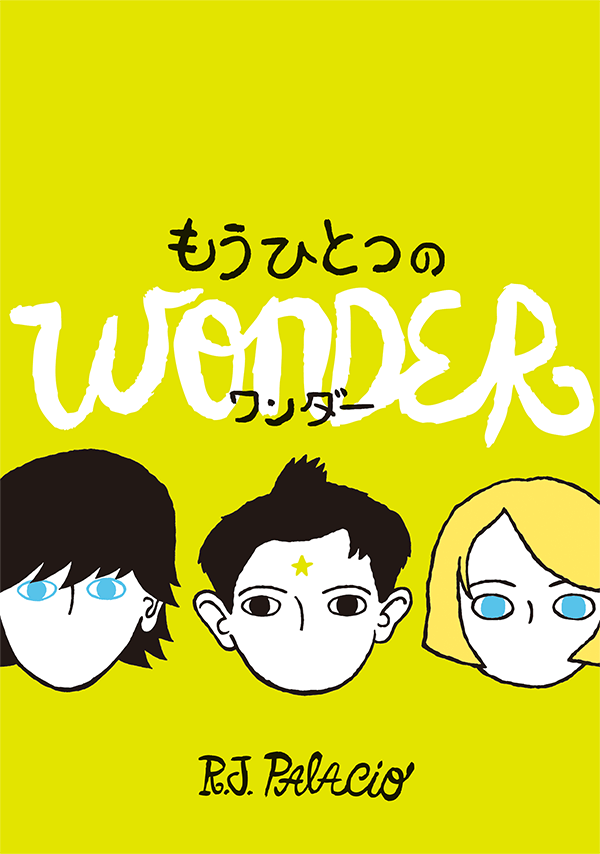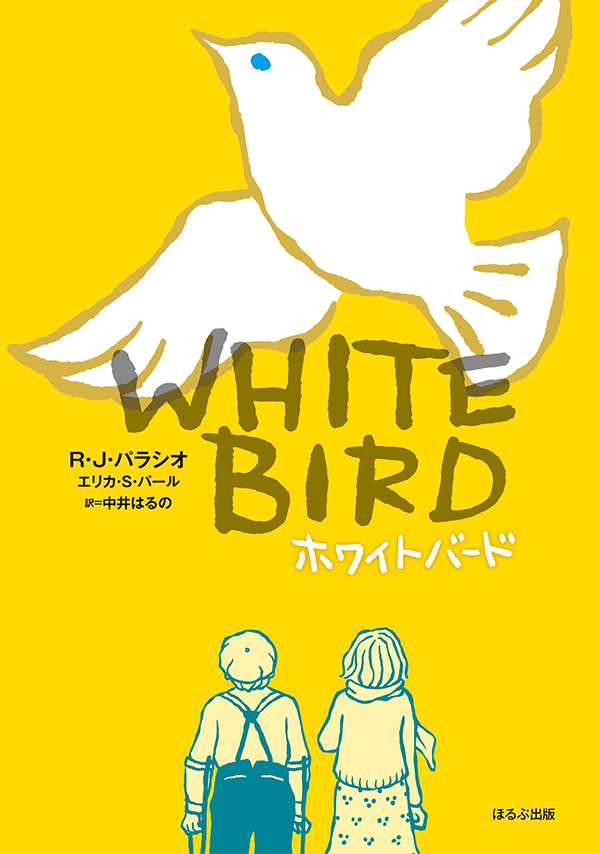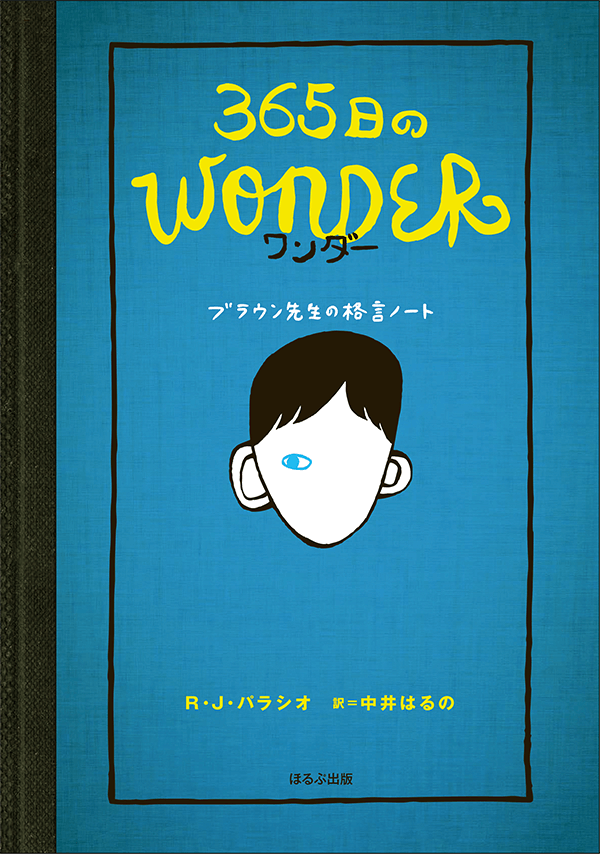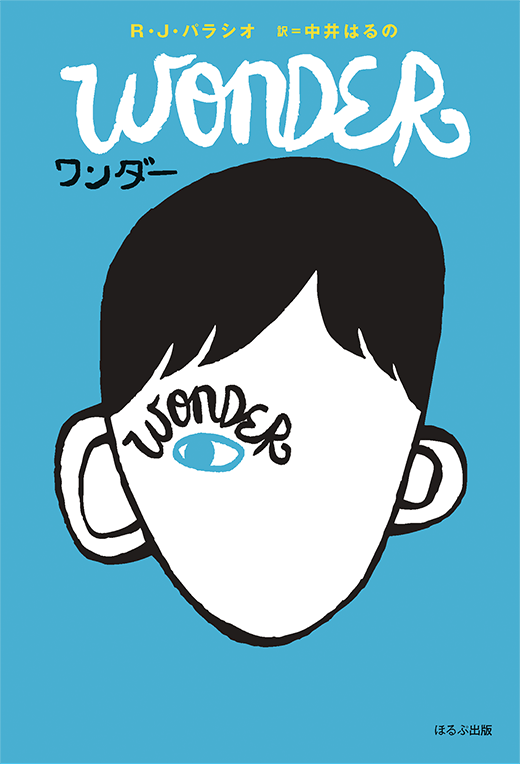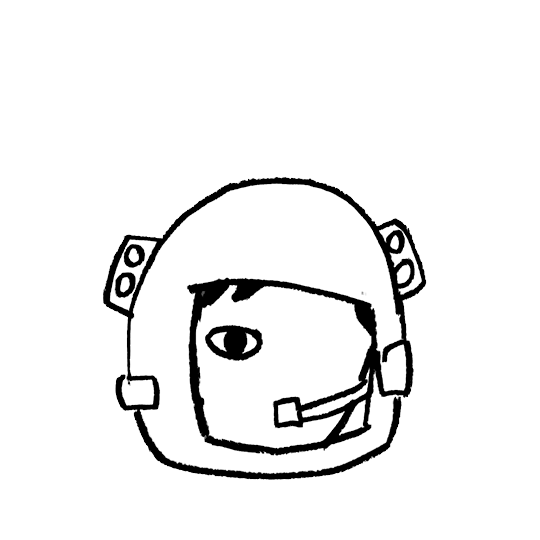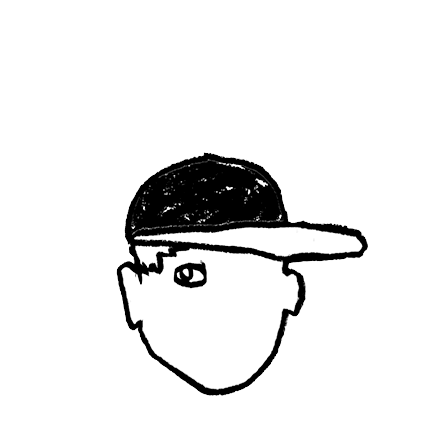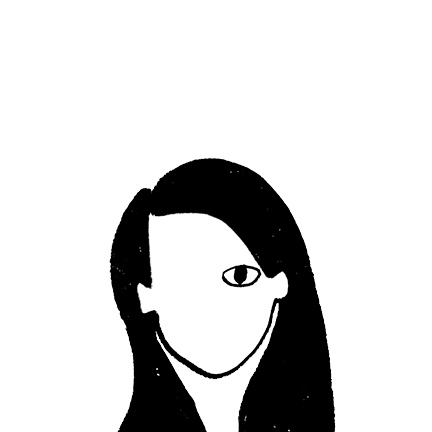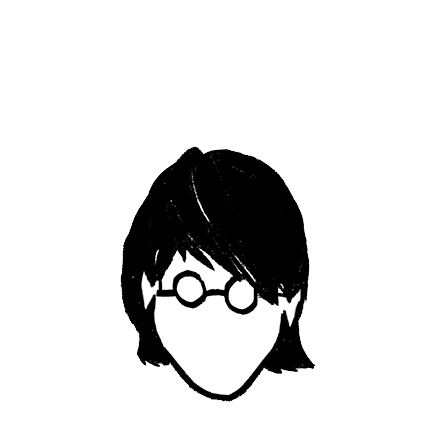『ワンダー』の主人公オーガストの物語から始まり、時代をこえて展開するワンダーシリーズ。
友だちの視点の短編集『もうひとつのワンダー』に、いじめっこジュリアンの心境の変化を祖母の戦争体験を通じて描かれた『ホワイトバード』。
格言をまとめた『365日のワンダー』。
1冊では終わらないワンダーの世界です。
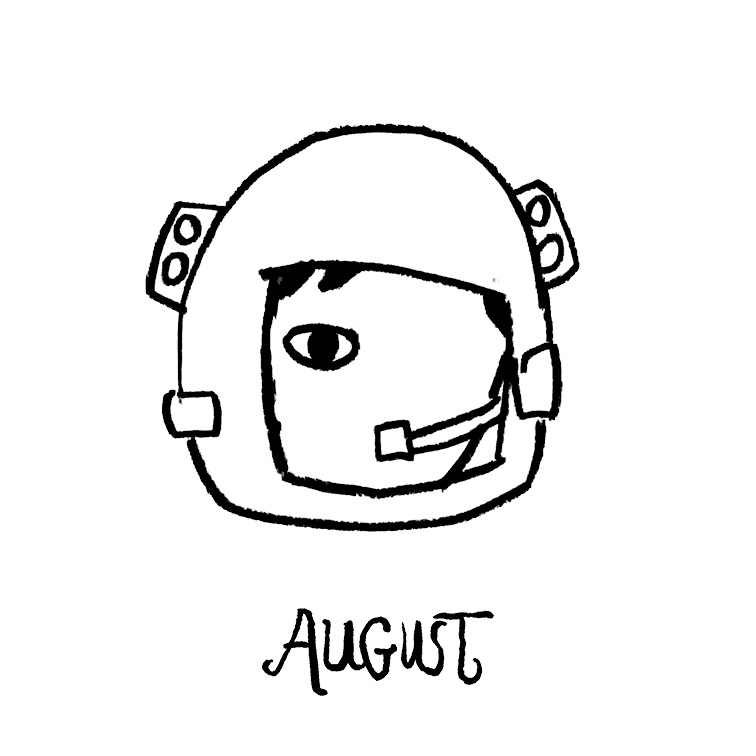
ふつうの男の子。ただし、顔以外は。
「世界中のだれもが、一生に一度はスタンディグ・オベーションを受けるべきだ」

アイドルみたいにカッコいい、いじめっこ。
「なんでそんな顔になったんだ? 火事かなんかにあったの?」
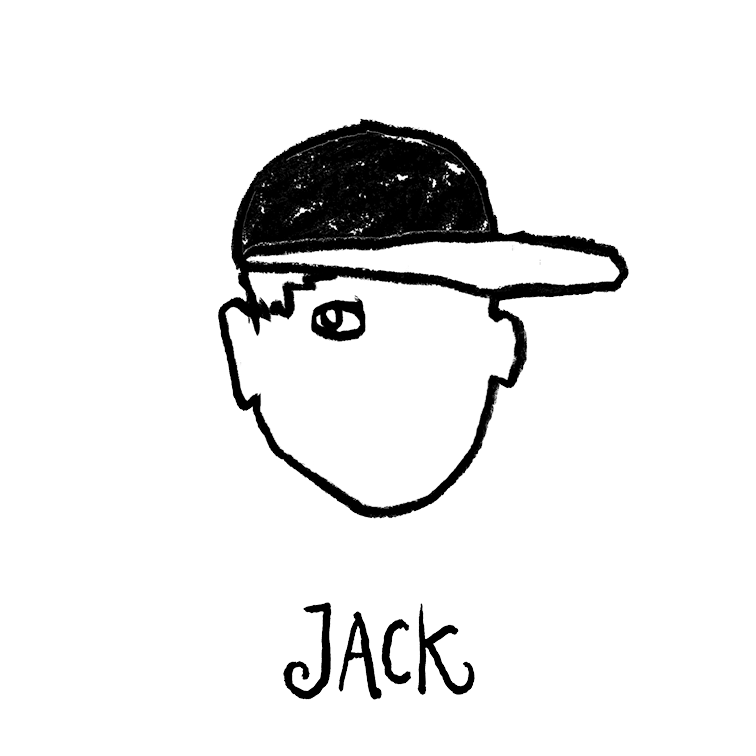
オーガストのクラスメートで、親友。
「おいジュリアン、いいかげんだまってろ」

オーガストとランチをいっしょに食べてる女の子。
「友だちになりたいから、なったんだよ」

オーガストの幼なじみ。
「友情ってのは、むずかしいときもある」

オーガストのクラスメートで、いい子の優等生。
「愛想よくするだけじゃだめ。友だちにならなくちゃ」
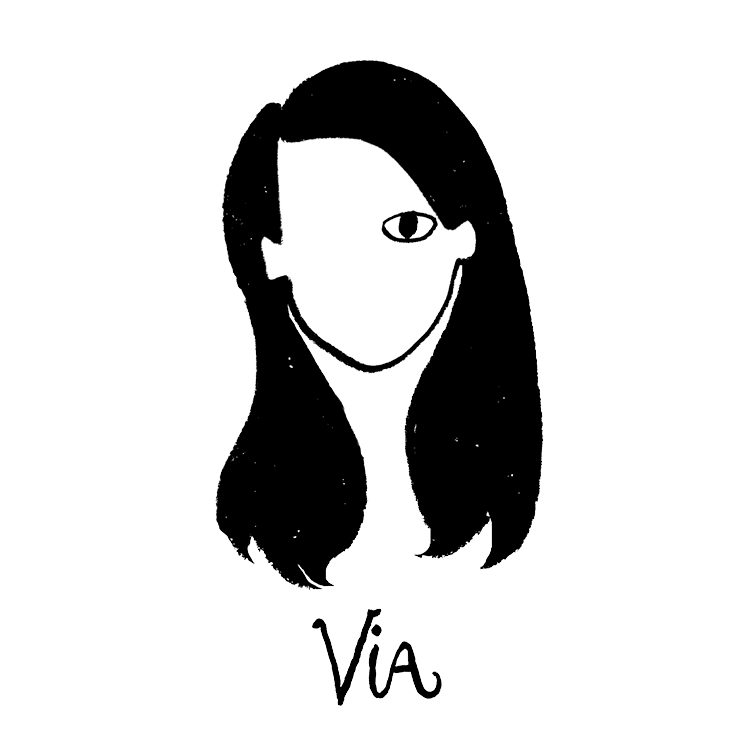
オーガストのお姉ちゃん。おばあちゃん子。
「大事なのは、どの人もみんな、いやな一日をがまんしなきゃならないってこと」

ヴィアの親友「だった」女の子。
「よっ、トム少佐!」
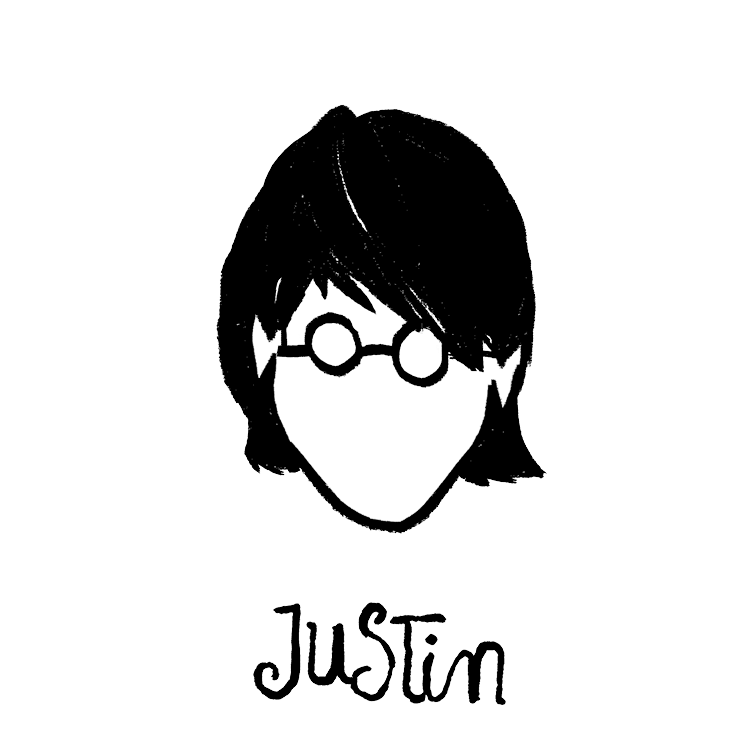
ヴィアの彼氏。ミュージシャン。
「この世界は、小鳥たちをみんな大事にしている」

ジュリアンのおばあちゃん。おしゃれで個性的。戦争を体験している。
「人生のすばらしさはね、ときにまちがいを正せるってことなんだ」

サラの同級生。ポリオの影響で松葉杖を使って歩いている。
「ぼくを信じて。それだけの意味があるから」
オーガストの学校の先生
「正しいことをするか、親切なことをするか、どちらかを選ぶときには、親切を選べ」
 作者紹介
作者紹介
アメリカの作家。長年、アートディレクター、デザイナー、編集者として、多くの本を担当してきた。デビュー作『ワンダー』は全世界で1500万部を越す大ベストセラーとなり、55言語に翻訳され、映画化もされた。夫と2人の息子、2匹の犬とニューヨーク市に住んでいる。
A. 数年前、息子たちとアイスクリームを買いに出かけた時のことです。上の子がミルクシェイクを買いに店内に入り、下の子とわたしは外のベンチで座って待っていました。当時下の子は3歳で、ベビーカーに乗せていました。ふと気づくと、となりに頭部の骨格に障害のある女の子が座っていました。女の子の友だち(姉妹だったのかもしれません)と、母親も一緒にいました。下の子は、その女の子を見上げた時、まさにみなさんが想像するような反応を見せました。おびえて、大声で泣き出したのです。わたしは急いでベビーカーごと遠ざけようとしました。息子のためというよりは、女の子を傷つけたくなかったからです。とっさに動いたものですから、そばにいた上の子が持っていたミルクシェイクをこぼしてしまい、なんというか、ひどい状況でした。ベビーカーを動かそうとするわたしを見て、女の子の母親は「それじゃあみんな、そろそろ行かなくちゃね」と優しく穏やかな声で言い、その場から立ち去りました。その言葉は、わたしの心にグサッと刺さりました。
その日一日中、わたしは自分がとった行動について考えました。あの親子は、毎日、何度も、同じような場面に出くわすのでしょう。それこそ何度も何度も。彼女たちはいつも、どのように感じているのだろう? わたしは、子どもたちにどう教えれば、次に似たような状況になった時、より良い対応ができるのだろう? 「じろじろ見ちゃダメ」と教えるのははたして正しいのだろうか、あるいはそういう考え方自体、もっと根深いものではないだろうか? そうしたいくつもの考えが頭の中をめぐり、わたしは、息子たちに良い態度を示す機会を逸してしまったことを後悔したのです。わたしがあの時すべきだったのは、下の子を遠ざけることではなく、女の子と、女の子の母親に話しかけることだったのです。仮に下の子が泣いても、それはそれ。子どもは泣くものです。彼には、彼のために、怖がることなど何もないよと言ってやるべきだったのです。単純に、わたし自身、ああした状況で、取り乱す以外にどうすれば良いか知らなかったのです。
偶然ですが、その日の夜、ナタリー・マーチャントの「Wonder」という曲がラジオで流れました。日中のアイスクリーム事件のことを考えていたわたしに、その曲はきっかけを与えてくれたのです。その夜からわたしは、「ワンダー」の執筆を始めました。
A. 何週間か、遺伝学についてリサーチしました。特に子どもにおける頭蓋顔面の異常に関して。これには多くの症例があり、程度もさまざまでした。書籍では、オギーの症例に対して具体的になりすぎないようにしました。わたしの考えでは、オギーは唇と口蓋が裂け、他にも未知の症状が併発し複雑化した重度のトリーチャーコリンズ症候群を患っており、このことがオギーの特異な症例を医学的に謎の多いものにしています。
A. この本は確かに、いじめに対する強いメッセージを持っています。私自身がいじめを受けたかどうかについては、答えはノーです。いじめを受けていたことはありません。ですが、多くのことが思い出されますし、明らかに身体的にいじめを受けている場合以外にも、たくさんの種類のいじめがあることも知っています。集団内での孤立や、冷やかし、友人たちの無視などもあります。そうしたものは、わたしも経験があります。もちろん、オギーが受けていたものほどではありませんでしたが。ジュリアンのような存在も覚えがあります。彼らはいきがり、誰かをこきおろすことで自身の優越を感じていました。それは、集団内で最も下の序列の者を攻撃するという、いじめにおける一般的な手口です。ジュリアンにとって、オギーがその対象でした。食物連鎖のもっとも下にいる存在です。オギーでなかった場合、それはジャックだったでしょう。オギーでもジャックでもなかった時は、他の子であった可能性もあるのです。もしかしたら、オタクっぽいという理由でふたりのマックスだったかもしれません。あるいは、海の保全を熱心に考えるリードだったかもしれません。誰かがそうであらねばならなかったのです。ジュリアンのような子どもは、こきおろすことで自分の自尊心を満たせる対象を、常に必要としているのです。それは、未熟な子どもにとってとても根源的な感情です。サマーはそのスペクトルでは対極に位置しています。彼女は、感情面、精神面ともに大変成熟しています。
A. わたしは子どもたちに、自分の行動は周囲のみんなも見ている・気づいているということを知っておいてほしいと思います。あからさまなものでなくても、ひどいことをすれば、誰かが苦しんでいます。親切にすれば、誰かが助かります。親切にするか、ひどいことをするのか、どちらを選ぶかは、子どもたち次第なのです。この世において、どちらであるかを選択しなければなりません。そしてその選択をするのは、友だちでも親でもなく、自分なのだということを知っておいてほしいと思います。
A. ご両親たちは、こうしたことをふまえて、もっと子どもたちに関わって欲しいと思います。学校でのいじめは避けられないもので、子どもたちには親の介入無しに自分で解決してほしいと期待している大人たちと、話したことがあります。ある父親がわたしにこう言いました。「まあ息子はわたしの言うことなんてもう聞く耳持たないし、わたしも彼にああしろこうしろと言うような、無駄に時間をかけることをやめたんです」。わたしに言わせれば、我が子がもう聞きたくないとする素振りを見せている時がもっともあなたを必要としている時なのです。わたしが思うに、親はみな本心では、いじめられているよその子を見て、自分の子じゃなくてよかった、と胸をなでおろしているのです。しかし、親はそうしたものの考えをやめなければなりません。親は、それが難しいことであるがゆえに、わが子に対して、優しく、善い行いをしなければならないと言って聞かせなければならないのです。
※コメントは全て2015年『ワンダー』刊行時のものです
翻訳家。東京都生まれ。外資系銀行勤務後、翻訳・通訳に転向。出産を機に児童書の翻訳に携わるようになる。2013年、『木の葉のホームワーク』(講談社)で第60回産経児童出版文化賞翻訳作品賞受賞。主な翻訳作品に「ワンダー」シリーズ(ほるぷ出版)、「グレッグのダメ日記」シリーズ(ポプラ社)、『よるのあいだに…』(BL出版)、『ビアトリクス・ポター物語』(化学同人)などがある。ビアトリクス・ポター協会、日英協会、JBBY会員。株式会社メディアエッグ代表。